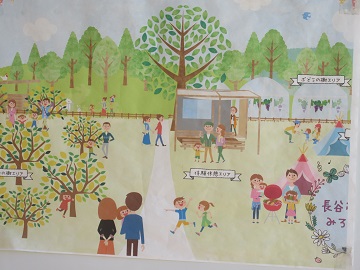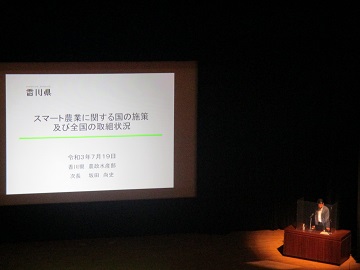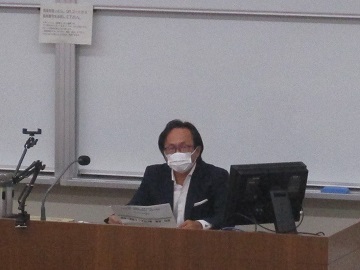フォトレポート(令和3年度)【目次】 |
2月
多面的機能発揮に係る中国四国農政局長表彰及び意見交換
- 撮影場所:香川県丸亀市
- 撮影日:令和4年2月24日
|
|
中国四国農政局では、水路や農道等の地域資源の保全管理など、農業の有する多面的機能の発揮を促進する活動に取り組まれている優良な組織等を表彰しています。 このたび、令和3年度の受賞組織として、香川県丸亀市の「あやうた地域広域協定」が優秀賞に輝き、令和4年2月24日に丸亀市あやうた支所において表彰式を開催しました。本広域協定は、土地改良区が中心となって地域の集落と連携して広域的な活動を実施しており他地域へのモデルとなる点や、多面的機能の増進を図る活動について今後も継続性が期待される点が高く評価されました。 式では、香川県拠点の小野寺地方参事官から表彰状が授与され、受賞者から「この制度によってため池や農道等の地域環境が守られていることに感謝します。」とのお言葉を頂きました。 その後、綾歌町土地改良区、丸亀市、香川県を交えて意見交換会を開催しました。意見交換会では、多面的機能支払制度は良い制度なので継続してもらいたいという意見や、広域化を進めているが農家の高齢化や後継者不足などの課題があるといった意見等が出され、活発な意見交換会となりました。 |
12月
香川大学農学部棚田の会との意見交換会
- 撮影場所:香川県三木町
- 撮影日:令和3年12月17日
|
|
令和3年12月17日、香川県拠点は香川大学農学部において、棚田の会、香川県、小豆島町を交えて棚田地域振興に係る意見交換会を開催しました。 棚田の会は、主に香川大学農学部の学生で構成されており、小豆島町の中山千枚田の保全活動等に取り組んでいるサークルです。意見交換会では、小豆島が世界の持続可能な観光地TOP100に選ばれたのを機に、棚田の会が香川大学の学生向けに開催した小豆島紅葉・棚田観光ツアーの様子や活動状況をお聞きしました。また、小豆島町中山地域で毎月1回開催されている若手の意見交換会で出てきた意見や、棚田観光の課題などについて情報交換を行い、活発な意見交換会となりました。 棚田の会の学生は「今後はまた小豆島紅葉・棚田観光ツアーのような棚田の良さを知ってもらうツアーを企画したい。」「棚田に興味がある人だけじゃなく、小豆島に興味がある人にも棚田の会に加入してもらうための企画を行いたい」と話していました。 |
四国夢中人との意見交換
- 撮影場所:香川県丸亀市
- 撮影日:令和3年12月10日
|
|
令和3年12月10日、香川県拠点は丸亀市において、地域活性化に取り組むNPO(非営利団体)四国夢中人と意見交換を行いました。 四国夢中人は、四国の魅力を世界に向けて発信することを目的に活動しています。その一つが、地域活性化の「モデルアイランド」として、瀬戸内海に浮かぶ塩飽(しわく)諸島の手島(丸亀市)において、そこに生きる人々や自然の魅力を世界に発信する活動です。 手島は人口減少や高齢化が進行しています。その手島を花と昆虫の楽園にしようという取組で、ボランティアや島の人々と四季折々の花の植栽を行っています。また、島の魅力を伝えるためYouTubeによる配信も行っています。 意見交換では、手島で地域活性化に取り組むことになったきっかけ、島が抱える課題や今後の展開方向などが話題となりました。 |
株式会社尾野農園との意見交換
- 撮影場所:香川県善通寺市
- 撮影日:令和3年12月8日
|
|
令和3年12月8日、香川県拠点は善通寺市において、露地野菜を栽培している株式会社尾野農園と意見交換を行いました。 尾野農園は、香川県善通寺市と丸亀市で青ネギ、スイートコーン、ブロッコリーを中心とした露地栽培を行っています。また、ネギの自動収穫の導入や気象と栽培管理のデータベース化などのスマート農業にも取り組んでいます。 意見交換では、Uターン就農したきっかけ、農地集約、スマート農業、販路確保、農業経営方針などが話題となりました。 |
11月
統計調査への協力に対して大臣感謝状を伝達
- 撮影場所:香川県丸亀市、観音寺市、高松市
- 撮影日:令和3年11月25日(丸亀市)、11月18日(観音寺市、高松市)
|
|
国民の統計の重要性に対する関心と理解を深め、統計調査への一層の協力を得ることを目的として10月18日は「統計の日」と定められています。 農林水産省ではこの日を記念し、農林水産統計調査にご協力いただいている方々に対して、その功労を讃え感謝の意を表するため感謝状をお贈りしています。香川県では、農林水産大臣感謝状を10名(永年協力者7名、特別協力者3名)の方に、中国四国農政局長感謝状を15名の方にお渡ししました。 11月18日には、海面漁業漁獲統計調査員として15年にわたりご協力いただいている観音寺市の三好知生さん、農業経営統計調査農家として5年にわたりご協力いただいている高松市の西原義信さん、また11月25日に漁業経営統計調査漁家として15年にわたりご協力いただいている丸亀市の今中延好さんに対し、香川県拠点の小野寺地方参事官から、農林水産大臣の感謝状をお渡ししました。 今中さんから「感謝状を頂きうれしく思います。今後も漁政の基礎資料のために出来る範囲で協力します。」とお礼のお言葉を頂きました。 |
棚田地域振興に係る意見交換会
- 撮影場所:香川県小豆島町
- 撮影日:令和3年11月24日
|
|
令和3年11月24日、香川県拠点は「日本の棚田100選」に選定されている「中山千枚田」のある小豆島郡小豆島町中山地区において、香川県、小豆島町、小豆島町中山棚田協議会を交えて棚田地域振興に係る意見交換会を開催しました。 まず小豆島町地域おこし協力隊の方から、棚田の耕作状況や水路の管理について説明を受けながら現地を視察しました。その後、農政局地域整備課、香川県拠点、地域おこし協力隊から棚田の現状や課題について情報提供を行い、意見交換を行いました。 持続可能な観光地の国際的な認証団体「グリーン・デスティネーションズ(Green Destinations) 」が行っている「世界の持続可能な観光地TOP100選」に、四国で唯一選出された小豆島において、棚田を維持するために、高齢化・担い手不足や農道・水路の整備による耕作条件の改善などの課題について、幅広い意見・質問が出され、活発な意見交換会となりました。 中山棚田協議会の九野会長からは、「小豆島町は離島であるがゆえ、棚田のオーナー制度を行うにも、参加者が自家用車で来るような状況になく、課題も多い。今後は島内でもオーナー制度をPRし、地元の方々の力を借りて棚田を守りたい。」と話していました。 |
香川大学ワイン「ソヴァジョーヌ・サヴルーズ」の瓶詰め作業
- 撮影場所:香川県さぬき市
- 撮影日:令和3年11月19日
|
|
香川大学により開発されたワイン専用ぶどう「香大農R-1」を用いた今年の赤ワインが完成しました。この「香大農R-1」は平成18年に農林水産省に種苗登録されているもので、元々は生食用に開発されましたが、粒が小さいためにワイン向けに栽培されています。 そのような経緯で平成18年から醸造が開始された香川大学ブランドワインは現在、地域資源の開発と消費者ニーズにマッチした人気商品として好評を得ているとのことです。 特徴は、一般的な赤ワインに比べ、抗酸化作用で知られるポリフェノールが2~3倍多く含まれていて、高濃度に関わらず飲み口が良く健康志向の方にお勧めのワインだそうです。 さぬきワイナリーの竹中剛工場長は今年の出来について、「夏の長雨の影響でぶどう自体の生育が懸念されたが、秋から天候が良かったのでこれまでで最高の収穫量で、しっかりとした味わいとなっている」と話していました。 完成したワインは、さぬきワイナリー物産センター、香川大学内生協及び県内主要酒店で発売されます。 |
統計調査への協力に対して大臣感謝状を伝達
- 撮影場所:香川県高松市
- 撮影日:令和3年11月16日
|
|
国民の統計の重要性に対する関心と理解を深め、統計調査への一層の協力を得ることを目的として10月18日は「統計の日」と定められています。 農林水産省ではこの日を記念し、農林水産統計調査にご協力いただいている方々に対して、その功労を讃え感謝の意を表するため感謝状をお贈りしています。香川県では、農林水産大臣感謝状を10名(永年協力者7名、特別協力者3名)の方に、中国四国農政局長感謝状を15名の方にお渡ししました。 11月16日には、漁業経営統計調査漁家として5年にわたりご協力いただいている高松市の蜂須賀義則さん、農業経営統計調査農家として5年にわたりご協力いただいている高松市の赤松貞廣さんに対し、香川県拠点の小野寺地方参事官から、農林水産大臣の感謝状をお渡ししました。 赤松さんから「感謝状を頂きうれしく思います。今後も農政の基礎資料のために出来る範囲で協力します。」とお礼のお言葉を頂きました。 |
9月
香川県立農業大学校での施策説明
- 撮影場所:香川県琴平町
- 撮影日:令和3年9月16日
|
|
中国四国農政局香川県拠点は9月16日、香川県立農業大学校の担い手養成科の学生29名を対象に、農林水産省の施策について説明を行いました。 今回は、「食料・農業・農村をめぐる情勢」「統計データでみる中国四国の農業の現状」をテーマとして施策説明を行いました。 学生からは「香川県の農業について理解が深まった」「統計調査に興味を持った」などの感想が寄せられました。 今後は、9月30日に「みどりの食料システム戦略」「スマート農業の実現と強い農業のための基盤づくり」、10月14日に「経営所得安定対策」「輸出促進及びGI・6次産業化」、11月8日に「食の安全と消費者の信頼確保」の全7テーマを各90分の説明を実施することとなっています。 |
8月
モネが夢見た青い睡蓮
- 撮影場所:香川県財田町
- 撮影日:令和3年8月11日
|
|
フランス印象派の巨匠として知られる画家、クロード・モネが夢見た「青い睡蓮」が、三豊市財田町の香川用水調整池、宝山湖の上流にある「財田里山ビオトープ」で、かれんな花を咲かせ訪れる人を楽しませています。財田里山ビオトープの青の睡蓮は、近くにお住まいのご高齢の農家の方が、高知県北川村の「モネの庭マルモッタン」で苗を購入し、自宅で栽培していた苗約50株を5年前に移植したのが始まりです。ビオトープでは、青い睡蓮以外に白い睡蓮、黄色い睡蓮など色とりどりの睡蓮が花を咲かせています。 睡蓮の一つの花の開花期間は4日間で、5日目には倒れて水の中に沈み、下から新たなつぼみが上がり花を付けます。睡蓮の管理は、10日に1度、水に入って古い葉を取り除き、肥料を与えます。秋には球根を掘り起こし、イチゴのハウスで加温して越冬、春に再び植え付けるといった大変な作業の繰り返しで、農家の方がお一人で世話を続けられています。 睡蓮は、例年10月末頃まで見られます。開花時間は睡蓮の種によって異なりますが、ビオトープの睡蓮は、朝9時から夕方4時頃まで花を咲かせる種のようです。 モネが夢見た青い睡蓮、お近くにお立ち寄りの際には、訪れてみてはいかがですか。 |
7月
首長との意見交換
- 撮影場所:香川県三豊市
- 撮影日:令和3年7月29日
|
|
香川県拠点は、7月5日から7月29日までの間で、県内の全市町に「みどりの食料システム戦略」などの政策の周知や意見交換を行いました。 最終日に訪問した三豊市からは、昨年度に発生した鳥インフルエンザの防疫作業支援に対して感謝の言葉を頂きました。また当市において、渡り鳥の到来シーズンを前に、市内の養鶏場を対象に「鳥インフルエンザ対策に関する研修会及び意見交換会」を開催し、発生予防対策の徹底に取り組まれるとの話がありました。 当県拠点は、意見交換で出された地域の抱える課題や農林水産行政への意見・要望について、省内に共有するとともに課題解決に向けた取組を行います。 |
直島コメづくりプロジェクト
- 撮影場所:香川県直島町
- 撮影日:令和3年7月28日
|
|
令和3年7月28日、アートの町で知られている直島町(香川県香川郡)において、「直島コメづくりプロジェクト」に取り組んでいる公益財団法人福武財団の梅島敬太さんに話を伺いました。 |
農福連携に取り組む主要農業者等との意見交換
- 撮影場所:香川県さぬき市
- 撮影日:令和3年7月26日
|
|
7月26日、香川県拠点はさぬき市において農福連携に取り組む長谷ぶどう園の長谷真里代表及び障がい者福祉サービス事業所株式会社りんごハウスの樫原さゆり代表取締役と意見交換を行いました。 長谷さんはりんごハウスが運営する就労継続支援B型である「ゆめぽけっと」に、ぶどうの化粧箱の組み立てやシール貼り等の作業を依頼しています。 また、本年から長谷さんがレモンの木オーナー制度を開始するために整備したレモン園の運営管理も同事業所に委託しています。 今後について長谷代表は、「今年3月に定植したレモンは4年後に収穫が可能となるので、同事業所と共同でレモン加工品の開発やカフェ、ワークショップ等に取り組み、継続できる環境を作りたい」と話していました。 |
「令和3年度かがわスマート農業推進大会」を開催
- 撮影場所:香川県丸亀市
- 撮影日:令和3年7月19日
|
|
7月19日、香川県が主催する「令和3年度かがわスマート農業推進大会」が丸亀市のアイレックスで開催されました。 この大会は、農業労働力不足の解消や生産性向上等に向けて、データ駆動型農業やロボット技術等の活用を推進し、スマート農業の現場実装をより一層進めるために香川県が開催したもので、次代を担う農業大学校の学生をはじめJAや県下の若手農業者、施設園芸農家など約160名が参加しました。 当日は、県からスマート農業に関する国の施策や取組について情報提供が行われたほか、施設園芸の栽培コンサルティング企業である(株)デルフィージャパンの斉藤章氏による「植物生理の理解から始める実践的な環境制御」と題した講演が行われました。また、会場には県の試験研究機関や通信会社、農機具・農薬メーカー等がブースを設け、機器展示やマッチングを進めていました。 |
ひまわり畑
- 撮影場所:香川県まんのう町
- 撮影日:令和3年7月14日
|
|
まんのう町では、町おこしの一環として、町内各地の休耕田約20ヘクタールで約100万本のひまわりを栽培しています。 「中山ひまわり団地」と名付けられたひまわり畑には、遊歩道や高さ約2メートルの展望台があります。展望台からの眺めは見事で、黄色いひまわりが咲き誇っているのが見られます。 ひまわりの見頃は7月中旬頃からで、7月いっぱい楽しめるようです。 また、ひまわりの花を楽しんだ後は、ひまわりの種を収穫、搾油して「まんのうひまわりオイル」として販売されています。 |
「三高みんなの食堂プロジェクト」を実施
- 撮影場所:香川県東かがわ市
- 撮影日:令和3年7月14日
|
|
香川県立三本松高等学校では、学校と地域、大学、PTA、同窓会等とが力を合わせて作り上げる新たな学食スタイル、「三高みんなの食堂プロジェクト」に昨年9月から取り組んでいます。 食堂の運営は地元の農業生産法人が行っていますが、学校としては、生徒全員がプロジェクトの参加者として食を起点に考え、活動するよう、生徒自らがメニュー提案や掲示用のメニュー描き、野菜栽培や食堂の装飾等を行うとともに、SDGsの視点で地産地消や食品ロスの削減などを目標とした取組を進めています。 また、7月14日には、地域との交流の場として「1日食堂」が開催されました。これは、数ヶ月に一度、地域の飲食店が地元食材を使用して食堂で料理を提供するものです。当日のメニューはキーマカレー、スープ、サラダ、デザートで、生徒たちはおいしそうに食べていました。 今後の展開について、泉谷校長は「生徒の主体的な活動を充実させ、地域の方が食堂を利用して交流することが出来るようにしたい」と話していました。 (詳しくはこちら) |
「善通寺四角スイカ」の出荷
- 撮影場所:香川県善通寺市
- 撮影日:令和3年7月7日
|
|
JA香川県善通寺筆岡集荷場では、地理的表示保護制度(GI)に登録された「善通寺四角スイカ」の出荷が6月30日から始まりました。 「善通寺四角スイカ」は地理的表示保護制度(GI)に登録されて3年目となり、善通寺西瓜部会は昨年で50周年を迎えた記念すべき節目の年であるそうです。このため、購入者への日頃の感謝として、善通寺四角スイカ専用の座布団を作製して商品に添えているそうです。 座布団は、生産者が費用を出し合い今年限定で作成したそうですが、とても粋(いき)な心遣いであると思いました。 善通寺西瓜部会の山下部会長によると、今年は7月中旬頃までに約450個が、鑑賞用として主に関東・関西方面の市場に向けて出荷されるとのことです。 |
ハウス栽培の小原紅早生の出荷
- 撮影場所:香川県坂出市
- 撮影日:令和3年7月7日
|
|
坂出市にあるJA香川県坂出みかん選果場で、ハウス栽培された小原紅早生の出荷が最盛期を迎えています。 小原紅早生は、平成5年に品種登録された香川県オリジナルの温州みかんの品種で、果皮が紅く、濃厚な甘みが特徴です。平成29年12月に「香川小原紅早生みかん」としてGIに登録されています。 選果場では、規格ごとに仕分けされた果実を作業員が一つひとつ丁寧に箱詰めしていました。ハウス栽培は、高松市内の5戸の農家が取り組んでおり、今年は35トンの出荷量を見込んでいます。 今年の出来について、JA香川県高松市西部地域温室みかん部会の小林部会長は、「玉ぞろいと糖度の乗りが良く、最高の出来映えになっている。」と話していました。 6月中旬から始まったハウス栽培の小原紅早生の出荷は8月上旬まで続き、主に地元の市場に出荷されます。 (農林水産省ホームページ) |
業務推進会議を開催
- 撮影場所:香川県高松市
- 撮影日:令和3年7月6日
|
|
7月6日香川県拠点は、県拠点会議室において日本政策金融公庫高松支店との業務推進会議を開催しました。この会議は、双方の連携強化のための意思・疎通を図る場として毎年開催しています。 会議では、高松支店から令和2年度の融資実績と令和3年度の業務運営について説明があり、県拠点からはみどりの食料システム戦略などの国の農業施策について紹介しました。 今年度の高松支店の業務運営方針について、板野事業統括は、「融資先の経営課題の解決に向けた外部有識者による支援や輸出事業者間のマッチング支援などのコンサルタント融資に力を入れたい」と説明。 今年度も情報共有を図りながら業務を進めることを確認しました。 |
JA香川県販売力強化推進室との意見交換
- 撮影場所:香川県高松市
- 撮影日:令和3年7月6日
|
|
7月6日、香川県拠点は高松市中央卸売市場に事務所を開設し、地元の販路拡大に取り組んでいるJA香川県販売力強化推進室と意見交換を行いました。 JA香川県が取り扱うブロッコリーなどの主な野菜は、首都圏や関西方面を中心に出荷していましたが、新型コロナウイルス感染症感染の影響で外食事業者の休業等により業務用野菜の需要が減少。また、都市部での営業・販売促進も難しくなっていました。 このため、出荷先を都市部から地元にも向けることにより価格の安定を図ろうと、昨年10月に同市場内に事務所を設置。地元バイヤーとの商談を行うなど相対取引による地産地消の取組を強化しています。 同室の多田推進委員長は「地元スーパーと連携したイベントを開催するなど香川野菜をPRしている。」と取組について説明。同室によると、本年4月~6月は前年の同月期に比べて同市場内の販売額が24パーセント増加するなどの成果が出ています。 今後は、夏野菜のキュウリ、ナス、オクラの出荷が始まり、これらの野菜も地元スーパーの店頭に並びます。 |
首長との意見交換
- 撮影場所:香川県三木町
- 撮影日:令和3年7月5日
|
|
香川県拠点は、県内各市町を訪問し、現場と農政を結ぶ業務の一環として首長との意見交換を行っています。今年度の初日となる5日には、東かがわ市長と三木町長と意見交換を行いました。 三木町では、香川県内で生産量が一位のイチゴ栽培、みどりの食料システム戦略、収入保険、異業種交流が話題となりました。異業種交流について、町長は「異業種同士をより一層の結び付けが必要と考えており、その取組は町の役割である。」と話していました。 |
6月
香川大学大学院への施策説明
- 撮影場所:香川県高松市
- 撮影日:令和3年6月30日
|
|
令和3年6月30日、中国四国農政局香川県拠点は香川大学大学院において地域マネジメント学科の学生32名を対象に、農林水産省の施策等について講義を行いました。 講義では、みどりの食料システム戦略、地場農産物需給拡大プロジェクト、輸出促進の施策や中国四国地域の農業をめぐる事情について説明しました。 学生の皆さんからは、農業委員会の現場での役割、耕作放棄地解消に向けた取組、農泊を利用する外国人の関心事項や反応について質問がありました。また、講義後のアンケートでは「農林水産省ならびに中国四国農政局が携わる取組の多さに驚いた」、「農業を生業としていく方が増え、お金が回る仕組みができれば魅力的になると思う」などの感想が寄せられました。 |
旬のももを収穫体験
- 撮影場所:香川県さぬき市
- 撮影日:令和3年6月29日
|
|
令和3年6月29日、さぬき市造田の飯田栄一さんのもも園で、地元の造田小学校3年生児童31名がももの収穫を体験しました。これは「総合的な学習」の一環として平成6年から毎年行っているものです。 児童たちは、一ヶ月前に自分たちでメッセージ付きの袋を掛けた、早生の「橋場白鳳(はしばはくほう)」という品種のももを一つひとつ丁寧に収穫しました。 大きく熟したももを手に児童たちは、「おいしそう」、「家族といっしょに食べたい」とうれしそうに話していました。 毎年、園地を提供している飯田さんによると、今年は開花時期が例年より10日ほど早く、収穫期も1週間程度早まっているとのことで、実の数は例年より少ないものの大玉でおいしいももに仕上がっているとのことです。 飯田さんは、「最近の子供たちは自然と触れ合う機会や、仕事を手伝うという習慣が少なくなっており、子供たちが地元に興味を持つきっかけになれば」と話していました。 |
製麺業者との意見交換
- 撮影場所:香川県高松市
- 撮影日:令和3年6月24日
|
|
令和3年6月24日、香川県拠点は、石丸製麺株式会社(高松市香南町)石丸芳樹代表取締役社長と意見交換を行いました。石丸製麺は、創業110余年、伝統産業である讃岐うどんをはじめ、そうめん、ひやむぎなどの乾麺や半生麺の製造・販売をしています。 特に、機械式製麺に手打ちの技術を取り入れた独自の「手打式乾麺」の開発、地元産小麦「さぬきの夢」を原料とした製麺技術や地域の特産品とコラボレーションした新たな商品開発など付加価値を探求した取組を積極的に行っています。 意見交換においては、全粒粉の利用促進、有機小麦栽培、みどりの食料システム戦略などについて話題となりました。 |
ねぎ生産農業法人との意見交換
- 撮影場所:香川県観音寺市
- 撮影日:令和3年6月23日
|
|
令和3年6月23日、香川県拠点は観音寺市において、加工業務用のねぎを露地栽培している株式会社Sun soと意見交換を行いました。 Sun soは、観音寺市のほかに三豊市や岡山県新庄村にも生産拠点があり、ねぎを周年出荷しています。また、女性が働きやすい職場環境作りや人材育成に取り組み、長期雇用に繋げています。 意見交換では、夏場の害虫対策、担い手・農地集約、スマート農業、販路確保、生産拠点の拡大などが話題となりました。 今後の経営方向について、尾池 章良代表取締役は「県外にも生産拠点を整備したことにより、ねぎの周年出荷体制を更に強化するとともに、ねぎ以外の栽培品目の拡大を図りたい」と話していました。 (中国四国農政局ホームページ) |
夏イチゴの試験栽培
- 撮影場所:香川県坂出市
- 撮影日:令和3年6月21日
|
|
坂出市にある化学品メーカーの協和化学工業株式会社が、国産へのニーズが高い夏に収穫できるイチゴの試験栽培に取り組んでいます。 同社の敷地内にある約5アールの温室で試験栽培しているイチゴの品種は「夏瑞(なつみずき)」で、本年2月に定植した苗は順調に生育し4月から収穫が始まっています。 この取組は、北海道の種苗メーカーと共同で高温環境下での栽培に適するイチゴの新品種を開発することを目指しています。 協和化学工業の担当者は、「当社のバイオ技術を駆使しながら、西日本の中山間地での栽培に適する夏イチゴの新品種を開発したい」と話していました。 |
酪農経営者との意見交換
- 撮影場所:香川県三木町
- 撮影日:令和3年6月11日
|
|
令和3年6月11日、香川県拠点は木田郡三木町において、有限会社広野牧場の広野正則代表取締役、広野豊代表取締役と意見交換を行いました。 広野牧場は、酪農経営を中心にアスパラガス(さぬきのめざめ)を生産しているほか、ピザやジェラートの製造・販売など農業に新たな価値を求めて取り組んでおり、地域活性化に貢献しています。 意見交換では、異業種交流の意義、みどりの食料システム戦略などが話題となりました。 今後の農林水産業について、広野正則代表取締役は「次世代に継続させていくためには、経営が成り立つ産業にしていく必要がある。経営者の発想や経営感覚が重要になってくる。」と話されました。 |
甘草の定植作業風景~薬用作物の産地化に向けて~
- 撮影場所:香川県三豊市
- 撮影日:令和3年6月9日
|
|
株式会社Sun so(観音寺市)は、令和3年6月9日から、三豊市の圃場(約10アール)において、薬用作物である甘草(カンゾウ)の苗の定植作業を行いました。 甘草の苗の供給元である株式会社純緑農業(愛媛県)によると、収穫は5年後の予定であり、栽培期間中は化学肥料や農薬・除草剤を使用しないことから、収穫までの主な管理作業は根気よく除草を行うことのみだそうです。 株式会社Sun soでは、今後5年間、毎年約10アールずつ甘草の栽培面積を増加させていく予定としています。 漢方薬の原料となる生薬は、約8割を中国産が占めていますが、価格の上昇などにより中国産の確保が難しくなってきています。そうした中、生薬の原料となる薬用作物の国内栽培の拡大が期待されているところです。 三豊市では、薬用作物の産地化に向けた様々な取組が進められており、香川支局もそのお手伝いをしています。三豊市において薬用作物を栽培する農家も増えてきていますので、三豊市において薬用作物を栽培してみたいと考えている方は、三豊市農林水産課にご相談してください。 |
地域商社との意見交換
- 撮影場所:香川県高松市
- 撮影日:令和3年6月8日
|
|
令和3年6月8日、香川県拠点は高松市香川町でネギを中心に栽培している、株式会社azemichiの二川大地代表取締役と意見交換を行いました。 二川さんは、平成26年に住宅メーカーを退職し、地元香川県に家族でUターンして、これまで経験のない農業の道に進みました。現在は、ネギ栽培(4ヘクタール)を中心に家族とパート従業員の8名で会社を運営しています。 また、経営者として農業にビジネスの経営感覚を取り入れ、自社生産物だけではなく周辺農家の農産物も取扱うことで販路を拡大し、地域農業の活性化にも寄与しています。 県拠点からは、「みどりの食料システム戦略」などの政策を説明するとともに、株式会社azemichiの取組や地域農業の課題などについて意見を交わしました。 二川さんは、「地域で生産された農産物の販路拡大に向けて、6次化にも取り組んでいきたい。」と新たな分野への意気込みを話されました。 |
みとよのみフェア~おうちで三豊のおいしいものを楽しむ~
- 撮影場所:香川県高松市
- 撮影日:令和3年6月7日
|
|
5月18日(火曜日)~6月8日(火曜日)に高松市花園町「イクナス(IKUNAS)ギャラリー」にて「みとよのみフェア」が開催されました。 「みとよのみ」とは2018年に始まり、三豊市の農家やものづくりに関わる人たちを中心に、既に地域にある良いものや、まだ種の状態でこれから実になっていくであろう「みとよの“み”」たちを発掘し、発信していくプロジェクトのことです。 「みとよのみフェア」では、ジュースやドライフルーツ、パエリアセットなどの三豊のおいしいものが紹介・販売されているほか、新型コロナウイルスの感染防止のため、店頭だけでなくWEBSTOREでも商品の閲覧・購入が可能です。 イクナスの担当者は「今後1次産業の方と協力して食の発信をしていきたい」と語りました。 |
主要農業者との意見交換
- 撮影場所:香川県三豊市
- 撮影日:令和3年6月4日
|
|
令和3年6月4日、香川県拠点は三豊市において、さんわ農夢株式会社の大橋正幸取締役と意見交換を行いました。 さんわ農夢は、平成23年に建設業から農業に参入し、ブロッコリーやサツマイモの栽培・加工などに取り組んでいます。 意見交換では、異業種から見た農業の特徴、異業種交流の意義、農産物や加工品の輸出、みどりの食料システム戦略などが話題となりました。 将来の農業像について、大橋取締役は「担い手を確保するためにも安定的な農家所得の確保やスマート農業による省力化が重要」と話していました。 |
豊稔池の自然放水
- 撮影場所:香川県観音寺市
- 撮影日:令和3年5月22日
|
|
豊稔池は、大正時代の二度の大干ばつを契機に建設が計画され、大正15年の着工からわずか3年8ヶ月で石積み式5連のアーチダムが完成しました。 中世ヨーロッパの古城を思わせる景観、その構造形式は農業土木史上価値が高く、平成18年に国の重要文化財建造物として登録されました。 貯水量159万立方メートルを擁し、市内の水田約500ヘクタールを潤すほか、レタスやブロッコリーなどの野菜栽培にも貴重な水源として利用されています。 毎年夏に行われる「ゆる抜き」には、豪快に水門から水が流れる様子を見るために多くの観光客が訪れており、季節の風物詩となっています。(昨年は新型コロナウィルスの影響で中止。) |
5月
日本一のアスパラ農家を目指して
- 撮影場所:香川県丸亀市
- 撮影日:令和3年5月14日
|
|
丸亀市在住の専業農家である鈴木茂昌氏は、アスパラガスを中心に野菜栽培を手掛けています。「さぬき讃ベジタブル」のアスパラガス(さぬきのめざめ、ウェルカム)35アール、ナバナ20アール、にんにく10アール、玉ねぎ30アール、なす20アールなど年間を通じ、多様な野菜を出荷しています。 さぬきのめざめは、香川県農業試験場が開発したオリジナル品種で、2005年6月に品種登録されました。全長50センチメートルと通常のLサイズの2倍以上の長さがあり、穂先が開きにくいのが特徴です。収穫直後の新鮮なものは、生でも美味しくいただけます。 鈴木氏は、香川県農業試験場が開発したさぬきのヘイヤ(モロヘイヤ)やケロッコ(ケールとブロッコリーの交配種)といった目新しい野菜も栽培しており、消費者に笑顔で手に取ってもらえることを期待して、日々野菜作りに励んでいます。 また、鈴木氏は、「市内で農産物の集荷、販売を行う流通事業者との結びつきが深く、事業者に出荷する約90経営体とも意見交換をしながら、より高品質な野菜作りを目指し、規模拡大を図るとともに、新たな販路を開拓していきたい」と熱く語られました。 FOOD ACTION NIPPON 2015 商品部門(農林水産業分野)入賞 |
4月
異業種の若手経営者グループ「讃岐乃風」がマルシェを開催
- 撮影場所:香川県さぬき市
- 撮影日:令和3年4月18日
|
|
高松市、さぬき市の異業種若手経営者らが、コロナ禍で売上げが減少している中、令和3年2月に「讃岐乃風」を立ち上げ、令和3年4月18日(日曜日)に香川県さぬき市において、初のマルシェを開催しました。 讃岐乃風のメンバーには、うどん屋さんのほか、保険外交員や農業者、食品加工業者、広報を担当する者などの多彩なメンバー11名が参画しており、今回のマルシェの各ブースにおいて野菜、加工食品、醗酵食品等様々な商品が販売されていました。 讃岐乃風代表の田岡さんは「今回は昼のマルシェだが、次回は夜の夏祭り的なイベントを考えている。コロナ禍でしんどい思いをしている人のために、少しでも何とか潤っていただければと考えている。」と語られていました。 |
お問合せ先
香川県拠点〒760-0019 香川県高松市サンポート3番33号
電話:087-883-6500