LLPに関するOECDガイダンス
OECD作業部会で策定された遺伝子組換え農作物の微量混入(LLP)に関するガイダンスは、LLPの発生時の環境影響にかかる評価の方法や既存の評価結果の利用の考え方を提供し、評価者や管理者を支援するためのもので、執るべき管理措置を各国に強制するものではありません。
LLPの発生時に、輸入国が微量混入している作物の当該国の環境への影響を評価する際は、その作物が環境中にどの程度放出されたかを把握すること、過去の審査経験や既存の情報を活用することが特に重要としています。
遺伝子組換え農作物の微量混入(LLP)とは
多くの国で、遺伝子組換え農作物の輸入に先立ち、当該国内での使用について承認を義務づける制度が存在します。このため、同一の遺伝子組換え農作物であっても、ある国では承認されており他の国では未承認であるという状況が生じ得ます。輸出国で承認されているものの輸入国においては未承認の遺伝子組換え農作物が、意図せずに貨物に微量に混入することを「遺伝子組換え農作物の微量混入(Low Level Presence)」といい、略称でLLPとよばれています。
【LLPが発生するケース】
遺伝子組換え農作物を栽培するためには、自国の承認を受ける必要があります。
加えて、輸出が想定される場合には、輸出を予定する国からも承認を受けておく必要がありますが、審査中などの事情で、承認されていない段階で荷口中へ混入した場合(図中の輸入国C)、LLPが生じることになります。
また、輸入を予定していない国((図中の輸入国D)では、承認申請が行われていませんので、こうした国向けの荷口中に混入した場合にもLLPが生じることになります。
LLPの発生時における、環境影響の観点からの日本の対応について
日本では、発芽可能な種子の形態で、かつ環境に放出されうる状態で未承認の遺伝子組換え農作物を輸入することは、例えそれが微量であっても、カルタヘナ法上は認められません。LLP発生時の環境影響については、農林水産省では、「遺伝子組換え農作物のカルタヘナ法に基づく審査・管理に係る標準手順書(SOP)」(平成21年12月公表)の第3章に照らして対応することとしています。
SOPに基づいてLLP発生時のリスク評価を行う際(SOPのIII.1.6)には、OECDのガイダンスに示された考え方を適用することが可能です。
具体的には、OECDのガイダンスでは、LLP発生時のリスクの程度は、
1) 当該遺伝子組換え農作物がもともと有する環境への影響はどの程度か
2) 当該遺伝子組換え農作物は、流通時のこぼれ落ちなどにより、環境中にどの程度放出されているか
により評価可能であるとしています。
同様に、SOPに基づいて未承認の遺伝子組換え農作物に係る情報収集を行う際(SOPのIII.1.1)にも、類似の作物種や導入形質に関する審査経験や既存の情報の活用が重要であるとの、OECDのガイダンスに示された考え方を適用することが可能です。
農林水産省は、SOPに定められた手続きを円滑に進めるため、以下の取組を進めているところです。
- 遺伝子組換え農作物がもともと有する環境影響の程度の把握
遺伝子組換え農作物の特徴(生理学的・生態的な特徴など)の整理や、これまでに承認した遺伝子組換え農作物に関する審査結果のとりまとめ - 遺伝子組換え農作物(発芽可能な種子の形態で輸入されているもの)の環境放出の程度の把握
セイヨウナタネ、ダイズ及びこれらの近縁種の生育状況と交雑に関する調査、トウモロコシ及びワタの流通・加工実態や生育状況の調査
お問合せ先
消費・安全局農産安全管理課
担当者:組換え体企画班・組換え体管理指導班
代表:03-3502-8111(内線4510)
ダイヤルイン:0367442102





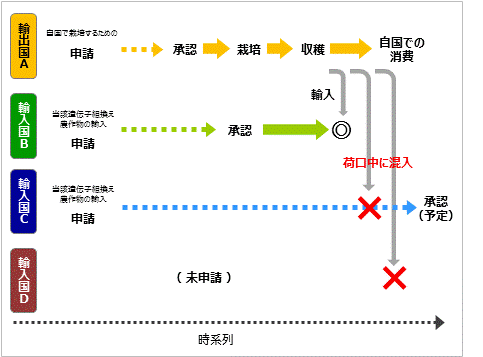 (GIF:33KB)
(GIF:33KB)