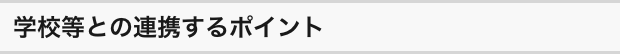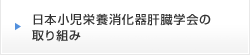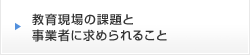企業や生産者が、食育活動の一環として学校等と連携するにあたり、比較的取り組みやすいものから、「工場見学」、「農業体験」、「出前授業」、「オンライン授業」の4つについて、具体的なポイントを紹介します。
食品企業で協力しやすい食育の体験として、工場見学があります。見学用の施設を完備していない企業でも、通常の作業現場を見てもらうことで対応することも可能です。

- 食品を作る工程を見てもらうことで、食に対する理解が高まり、仕事としての食への興味、関心が高まるきっかけになります。
- また、食の安全や環境問題への関心も高める機会にするとよいでしょう。
- 従業員と子供が会話をするなどして接する機会を設けることは、従業員にとっても働きがいになることが少なくないようです。

- 安全に気を付けることと、業務にあまり負担とならないようにすることも重要です。
- わかりやすく説明することは必要ですが、毎日の生活に身近なことから話をすると、理解されやすくなります。
- わかりやすくイラストや写真を使った説明パネルを用意するとよいでしょう。
- 簡単なクイズを出したり、質問をしてみたり、子どもたちの関心を高めるようなゲーム感覚で行うことも効果的です。
- 話を聞くだけではなく、手足や体を動かすような工夫が重要です。工場見学を行った後で、作っていた商品を実際に触ってみたり、食べてみたりすることで、実際の工場や工程の理解が高まることにつながります。
- 学校の教員とは密に連絡を取り合い、計画的に行いましょう。ただし、教員の方は忙しいため、負担をなるべくかけないようにすることが重要です。子供たちからだけではなく、親や家族からの質問を想定した工場見学に関するQ&Aを用意しておくことをお勧めします。

- 安全に気を付けることと、業務にあまり負担とならないようにすることも重要です。
- わかりやすく説明することは必要ですが、毎日の生活に身近なことから話をすると、理解されやすくなります。
- わかりやすくイラストや写真を使った説明パネルを用意するとよいでしょう。
- 簡単なクイズを出したり、質問をしてみたり、子どもたちの関心を高めるようなゲーム感覚で行うことも効果的です。
- 話を聞くだけではなく、手足や体を動かすような工夫が重要です。工場見学を行った後で、作っていた商品を実際に触ってみたり、食べてみたりすることで、実際の工場や工程の理解が高まることにつながります。
- 学校の教員とは密に連絡を取り合い、計画的に行いましょう。ただし、教員の方は忙しいため、負担をなるべくかけないようにすることが重要です。子供たちからだけではなく、親や家族からの質問を想定した工場見学に関するQ&Aを用意しておくことをお勧めします。
農業、漁業、酪農などの生産者が協力しやすいものの一つとして、農林漁業体験があります。特に農林漁業体験の中で子どもたちから人気が高いのは、収穫体験や、動物とのふれあい体験です。農業体験を通じて、子どもたちが自然と触れ合い、食や環境に関心を持つ貴重な機会となるよう、準備や安全管理をしっかりと行うことが大切です。

- 動物や植物など、すべての生命の大切さを知ることを学ぶ大事な機会となります。
- 地域に根付いている農業や食文化を理解することにつながり、地域への愛着を高めることになります。
- 生産者の作物を育てる努力や、育て方のこだわりなどを伝えるよい機会です。
- 子どもたちは実際に土に触れることで、自然を知る機会となるとともに、日常とは違った体験によって心が休まったり、優しい気持ちになることにつながります。

- 特に低学年の子どもは話を聞くだけでは飽きてしまいます。実際に自分で手足を動かして農作業を体験できるような機会を作ることが、子どもの満足度にもつながります。
- 作業的にゆとりがありすぎると、時間を持て余した子どもが遊んでしまい、それが事故やケガにつながってしまうことがありますので、ある程度の作業を用意しておくことが大事です。
- 指導者は、ついつい子どもの作業を代わってあげがちですが、サービスしすぎることがよいとは限りません。

- 特に低学年の子どもは話を聞くだけでは飽きてしまいます。実際に自分で手足を動かして農作業を体験できるような機会を作ることが、子どもの満足度にもつながります。
- 作業的にゆとりがありすぎると、時間を持て余した子どもが遊んでしまい、それが事故やケガにつながってしまうことがありますので、ある程度の作業を用意しておくことが大事です。
- 指導者は、ついつい子どもの作業を代わってあげがちですが、サービスしすぎることがよいとは限りません。
出前授業は、学校や地域の施設に専門家や企業、団体などの講師が出向いて授業を行う取り組みのことです。通常の授業では学べない実践的な知識や体験を学校で提供することを目的としています。

- 体験と比べると時間や作業的な負担も小さく、協力しやすいのが特徴です
- 生産者、食品企業、調理人、販売スタッフなど、様々な食に関する立場の人など、誰でも実施できます。
- 繰り返し使えるように内容や資料をまとめておけば、繰り返し利用することができて、作業負担なども小さくなります。

- 専門的な話よりも、基本的なことをやさしく話をするようにしましょう
-
内容は「起・承・転・結」の4つに分けて、それぞれ順を追って話をするようにすると、子どもたちも理解しやすくなります。
「起」・・・どんなものを作っているのか
「承」・・・作っているときに気を付けていることやこだわり
「転」・・・これまでに失敗したことや印象に残っている出来事、協力してくれる仲間たち
「結」・・・これからどうしていきたいか
- わかりやすくイラストや写真を使った説明パネルを用意するとよいでしょう。
- 特別なものがなくても、商品そのものや、工場内の写真などを見せながら話をすると、理解されやすくなりますし、話もしやすくなります。

- 専門的な話よりも、基本的なことをやさしく話をするようにしましょう
-
内容は「起・承・転・結」の4つに分けて、それぞれ順を追って話をするようにすると、子どもたちも理解しやすくなります。
「起」・・・どんなものを作っているのか
「承」・・・作っているときに気を付けていることやこだわり
「転」・・・これまでに失敗したことや印象に残っている出来事、協力してくれる仲間たち
「結」・・・これからどうしていきたいか - わかりやすくイラストや写真を使った説明パネルを用意するとよいでしょう。
- 特別なものがなくても、商品そのものや、工場内の写真などを見せながら話をすると、理解されやすくなりますし、話もしやすくなります。
最近、増えているのが、オンライン授業です。Webカメラを通して、教室と農場や工場とつなぎ、実際の作業風景を見てもらうとともに、子どもたちから質問を受けて、現場の人が答えるという内容が多いです。
慣れてくれば、複数の現場をつないで(例えば、農場と、選果場、直売所などの売り場、飲食店の調理場など)、農作物の流れを包括的に把握してもらうことも可能となります。

- 交通費や時間などの負担が小さく、距離が離れている学校で実施することも可能です。
- 例えば種まき、育成時、収穫時など、異なる季節の様子を見てもらうことも可能です。

- 資料や写真、イラストなどを見せることで、理解度は高まります。
- 動画の場合は10分ほどの長さになるよう、コンパクトにまとめたほうが効果的です。
- 動画を見てもらった後で、子どもたちから質問を受けるようにすることで、理解度や注目度が高まるようです。
- あらかじめ撮影しておいた動画を使う場合は、音声が聞き取りにくい場合がありますので、テロップを入れた方が子どもたちの理解が高まります。
- 授業の最後に、要点を箇条書きにまとめた「まとめ」を加えることをお勧めします。
- 単発ではなく、複数の短い内容でのシリーズ化にすると、授業の時間に合わせて2、3本を組み合わせることができるため、活用されやすくなります。
- 資料や写真、イラストなどを見せることで、理解度は高まります。
- 動画の場合は10分ほどの長さになるよう、コンパクトにまとめたほうが効果的です。
- 動画を見てもらった後で、子どもたちから質問を受けるようにすることで、理解度や注目度が高まるようです。
- あらかじめ撮影しておいた動画を使う場合は、音声が聞き取りにくい場合がありますので、テロップを入れた方が子どもたちの理解が高まります。
- 授業の最後に、要点を箇条書きにまとめた「まとめ」を加えることをお勧めします。
- 単発ではなく、複数の短い内容でのシリーズ化にすると、授業の時間に合わせて2、3本を組み合わせることができるため、活用されやすくなります。